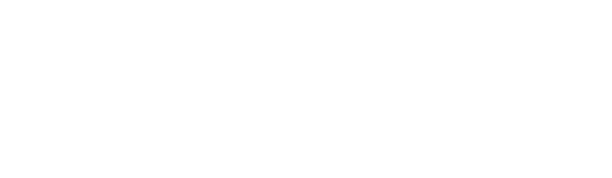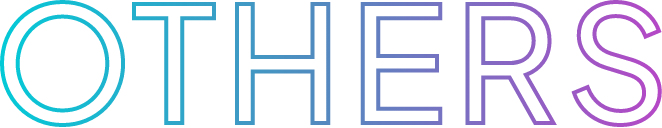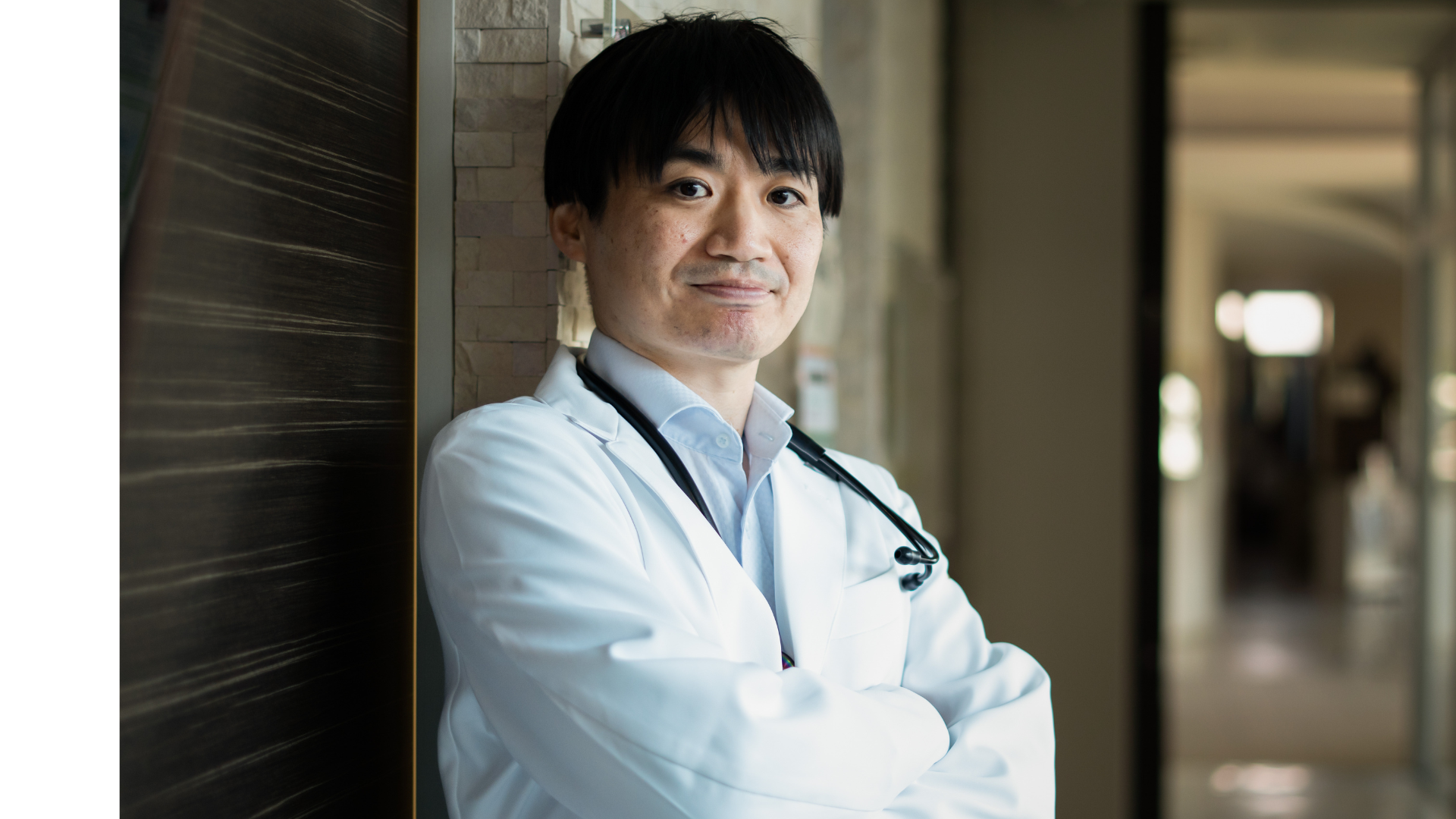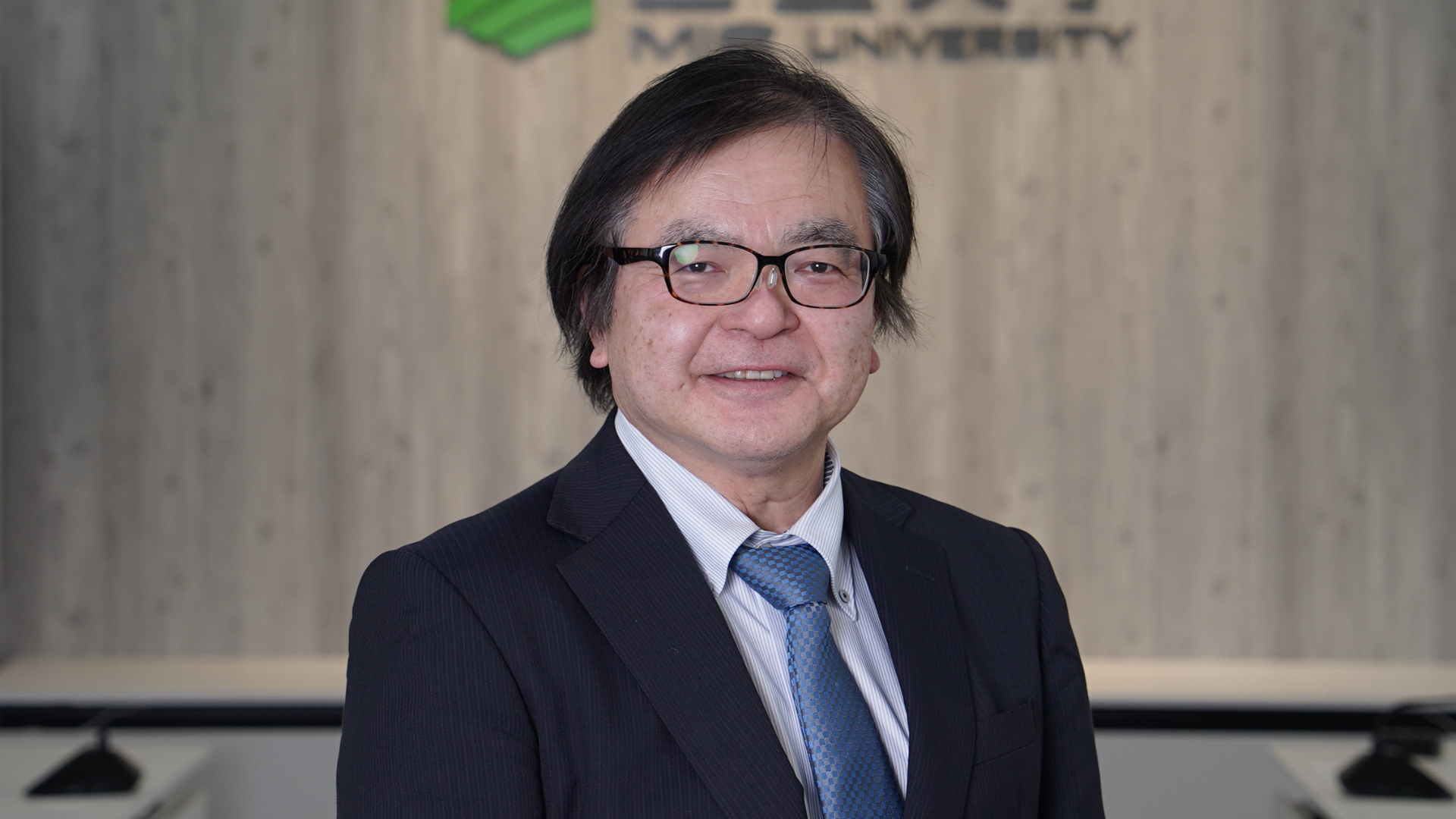流行に惑わされることなく確かな製品を永く作り続けたい


熊本誠太
銀峯陶器株式会社 四代目窯元熊本誠太(くまもと せいた)
1993年、三重県出身。大学時代は経営学を学び、ノースカロライナ大学へ語学留学。ヨーロッパをバックパッカーとして旅し、フィレンツェではデザインの世界に触れる。卒業後は陶芸の基礎を学び、2017年、銀峯陶器に入社。同社・熊本哲弥現代表の後継となる四代目。2019年に陶磁器の企画開発および卸・販売を手がける株式会社G.M.P.を設立、自社ブランド「PETARI」を立ち上げる。2024年、同ブランドがグッドデザイン賞を受賞。
若くして海外で得た、多くの学び

銀峯陶器は1932年の創業です。現在は三代目である父がトップとして活躍していますが、ゆくゆくは私が四代目を継ぐ立場です。ですから大学時代から経営学を学び、海外への販路展開も考えてアメリカでの語学留学も果たしました。ヨーロッパを旅したのも単なる観光ではなく、イタリアでデザインを学びたいという大きな目的があったからです、いわゆる放浪の旅ではなかったですね。
旅の期間は4ヶ月ほどで、それほど長いわけではありませんでしたが、とても刺激的でした。特にイタリア・フィレンツェでは、博物館や美術館で多くの工芸品や美術に触れ、美に対するアプローチの違いを肌で感じることができました。
イタリアには、ファッションや食といった華やかなイメージがありますが、実際に学んでみて印象が大きく変わったのが「装飾性だけではない、意味のあるデザイン」という考え方でした。たとえば鍋のデザインでは、鍋の底から取っ手まで、すべてに意味を持たせることが求められました。無作為に「ここは10センチにしよう」というのではなく、「ガスコンロの直径が一般的に14センチだから、それに合わせたサイズにすることで熱効率が上がる」といった具合に、目的を持って論理的に構築していくのです。そうしたアプローチは、日本のデザインとも通じるところがあり、自分にとって非常に印象深い学びでした。
入社とともに感じた危機感への対処

帰国後、会社に入り、大きな課題として感じたのが、自社の販売体制です。当時は限られた数件の問屋さんを取引先として、そこに販売を依存していたのです。その取引先も後継者不足の問題を抱えており、売上は拡大するどころか縮小の一途。長い目で見ると、売上の右肩下がりは避けられません。
また問屋さんに販売を依存してしまうと、小売価格の下落を招く傾向があります。そうなると中間業者の利益も小さくなりますし、結果としてプロモーション活動の予算を確保しにくくなり、販売が失速してしまいます。この状況に対応するには、他社に依存しない販売体制を築き、工場を安定的に稼働させていける仕組みを作ることです。こうして生まれたのが、販売のみを行う株式会社G.M.P.です。
銀峯陶器が販売部門を立ち上げ、問屋機能を持つと、業界内での反発に遭う可能性がありますが、別会社にすれば、そうした摩擦を避けられます。また販売機能を強化し、将来的に他の窯元の製品も扱うようになれば、全体の販売量を拡張し、生産地全体を支えることができます。
現状ではメーカーと販売という二足のわらじを履いている状態ですが、この経験はいずれ私自身の大きな強みになるはずだと信じています。
独特の世界観を持った3つのブランド

モノづくりにおいて私が大切にしているのは、「実用性」「耐久性」「日常に馴染むデザイン」の3点です。これは私自身の考えというよりも、4代続く家業の中で、代々受け継がれてきた価値観です。私の前の3代の当主たちも、常にそこにこだわり続けてきましたし、私自身も自然とその価値観を大事にするようになっていました。理屈というよりも、代々受け継がれた血の中に流れているものなのかもしれません。
この3つの軸は、現在展開しているブランドにも色濃く反映されています。現在、弊社では「GINPO」「PETARI」「J.MEZON」の3ブランドを展開していますが、すべてに共通するDNAとして、実用性、耐久性、デザイン性を意識しています。
ブランドを分けたのは、それぞれに異なる販売戦略を持たせたいという理由もありました。まず「GINPO」は弊社にとっていちばん大きなブランドで、昔ながらの土鍋がメインですが、他の問屋さんと販売ルートが被らないよう、輸出を主軸としています。「PETARI」は新たなスタイルを提案する耐熱陶器、「J.MEZON」はメーカーと作家の中間のような、器としての十分な機能性と焼きものならではの揺らぎの美しさを、ミニマルに表現しています。
まだ不安定な部分もありますが、3つのブランドがそれぞれ異なる切り口、違った世界観を持ち、着実に成長を続けています。その先に、これまで造り続けてきた「土鍋」が「鍋料理の道具」という枠から飛び出し、季節を問わず使える調理器具として世間に認識されることを願っています。
不安定さと安定感との絶妙なバランス

銀峯陶器の強み、独自性は「手仕事の柔らかさと製品としての安定性を保っている」という点です。
焼き物は土と釉薬、つまり粘土や鉱石といった天然物から作られていますから、どうしても原材料の質にブレが生まれます。これが金属やプラスティックと違うところです。
また粘土は当然、山から掘り出してくるのですが、一度掘り出してしまったら、元に戻すことはできません。鉱石にしても同じです。そのため近年では新規鉱山を開拓するにも自治体や地域住民の方々の同意が得られず、原材料の入手からして難しい、といったこともあります。
製造プロセスも、一筋縄ではいきません。原材料の配合から焼成までの一連の工程では、わずかな調合の違いやその年の気候などによって、仕上がりが変わってくることがあるのです。ですがそのまま完成品として出荷してしまっては、お客様に不完全なものをお届けすることになってしまいます。ですから人の手と工夫が届くところはできるだけコントロールできるように、生産ラインを綿密に構築し、ISO9001も取得しました。
自然の材料だからこそ生まれるブレや、手仕事ならではの柔らかさを残しつつ、徹底した品質管理で製品としての安定感を保つ。これは私たちが最もこだわっている部分であり、今後も続く最大の挑戦といえます。こうした背景があるからこそ、私たちの製品には、単なるプロダクト以上の意味が宿っているのだと自負しています。
自分たちが作るものが、永く残るものであるように

今の自分にできることに誠実であり、無理に背伸びしない。こうした意識が、私の深いところにあるように感じます。モノ作りにしても会社の方向性にしても、決して突飛なことをせず、地に足をつけて一歩ずつ…というのが、弊社のスタイルです。これは「銀峯陶器」という社名にも表れています。
銀峯というのは、高山の頂上付近の万年雪を指します。それは夏でも冬でも、100年前でも100年後でも、常にそこに在って、山頂を彩っている。それと同じように、自分たちが作るものが暮らしの中に長く残る存在でありたい。そうした願いが込められています。
派手に稼ぐわけではなく、過度に注目を集めるでもなく、ただ淡々と、でも良いものだけを作り続ける。それは銀峯陶器の精神ですし、私自身もそれに共感しています。流行り物やトレンドに色目を使わず、確実な品質を持つものをお客様に届ける。1年2年で壊れたり、飽きたりするものは作らない。“使い潰せるもの”を作り続けたい。私たちはそう考えています。
まず自分と向き合い、自分の軸を築いていくこと

私自身もまだ若輩者ではあるのですが、若い人たちに何か言えるとしたら「まずは自分と向き合ってみてください」ということだろうと思います。自分が何を考え、何に違和感を覚えるのかを丁寧に見つめることが大切です。
そうした姿勢で日々を重ねるうちに、「自分の考え」と呼べるものが少しずつ育っていきます。やがて、納得できるものは何か、どうしても腑に落ちないことは何か――その輪郭が、自然とはっきりしてくるはずです。そして思考に芯が通ってくると、不思議と周囲や地域にも、何かしらの変化をもたらす存在へと変わっていくのではないでしょうか。
正しいかどうかに関係なく、人はそれぞれが築き上げてきた軸を頼りに人生を選択していきます。いつの時代も、正解というものは振り返ってみないと分かりません。だからこそ、自分なりの納得感を軸にして選び、進んでいくことが大切だと思います。
銀峯陶器株式会社
https://ginpotoki.com/