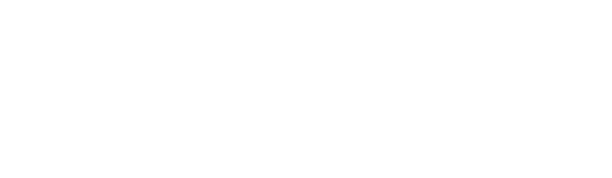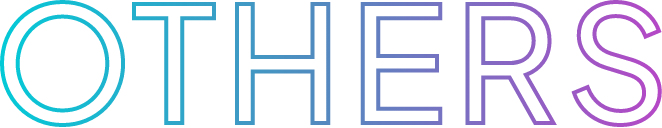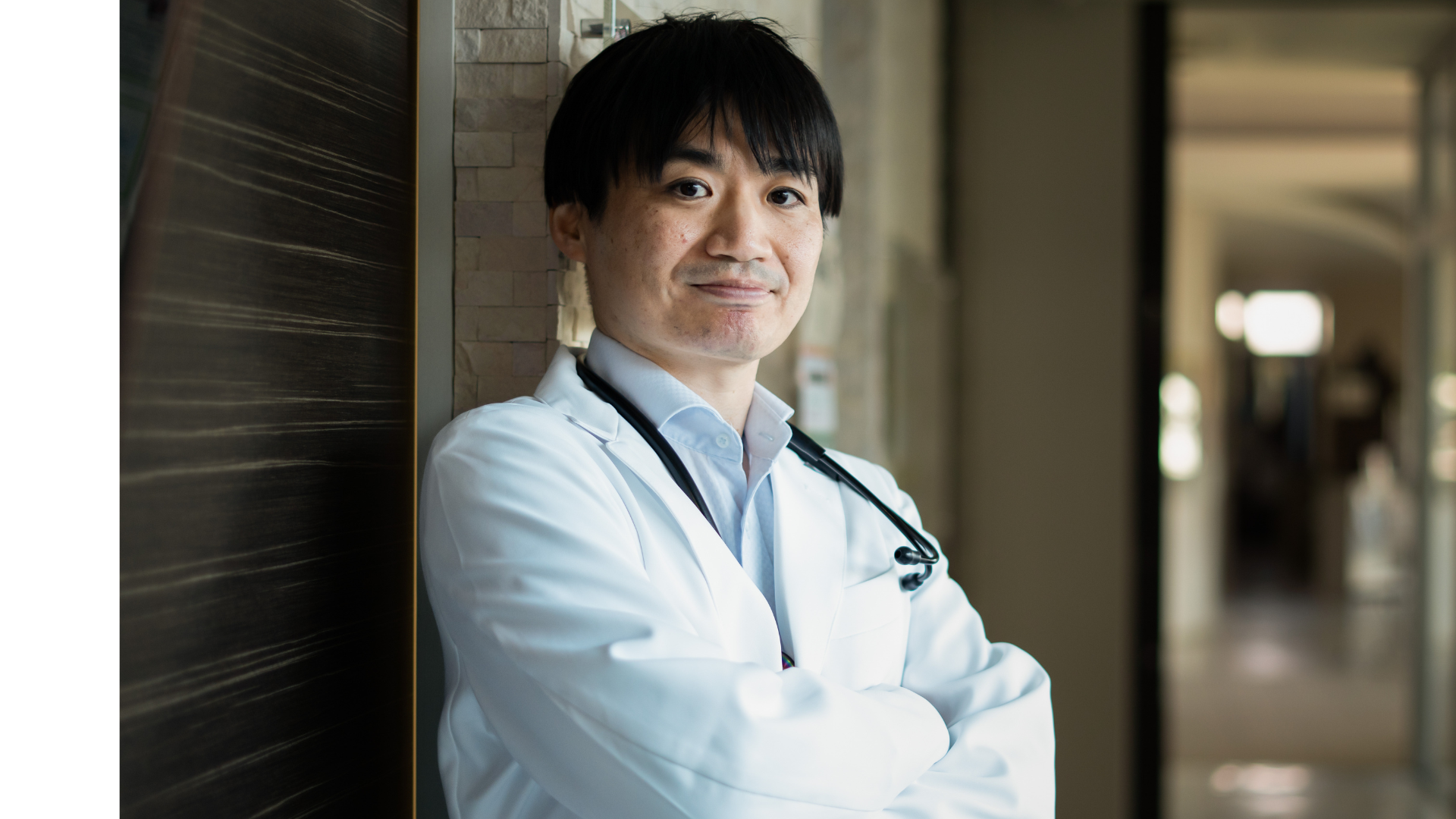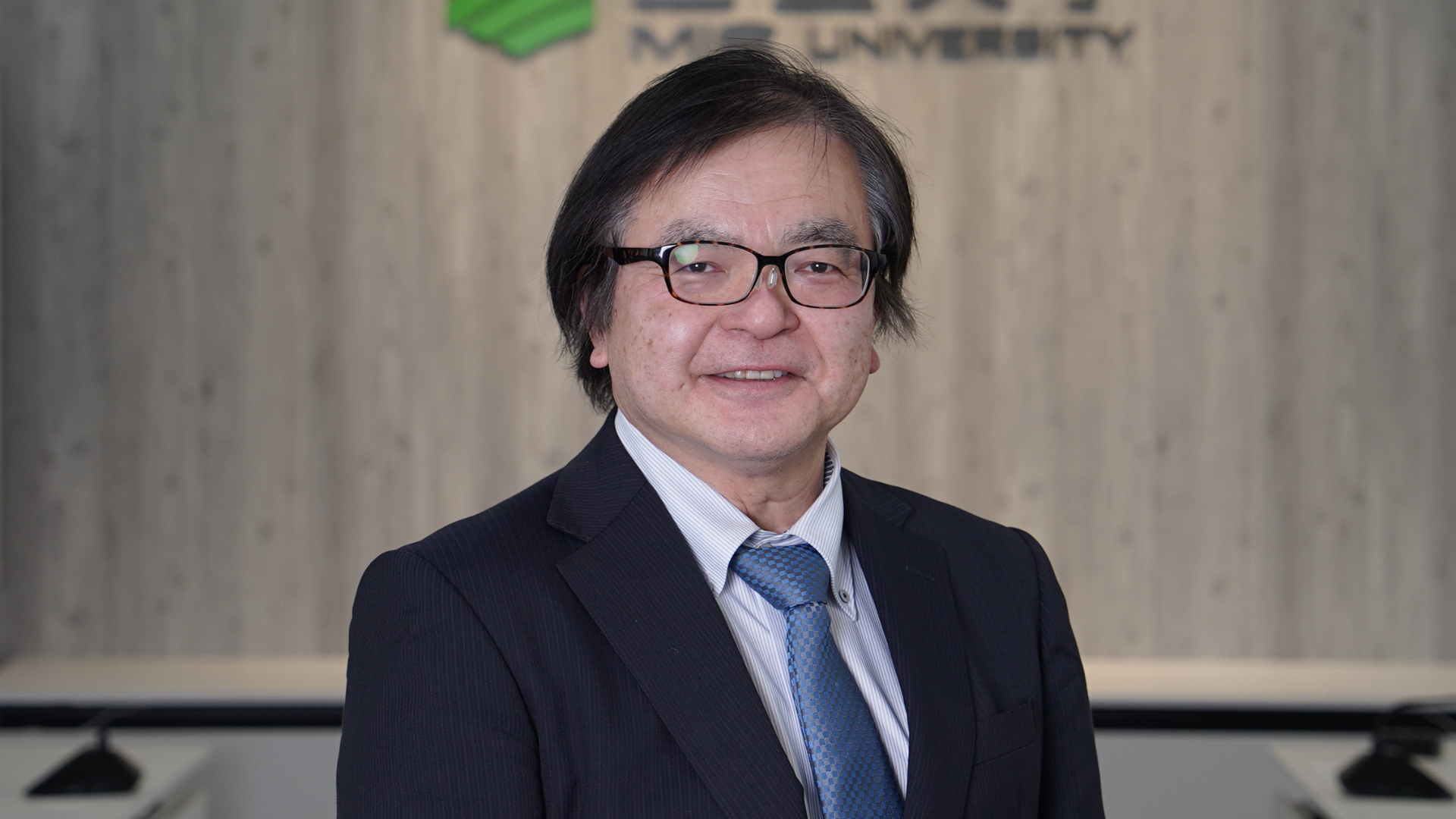病気だけでなく患者さんを診て地域医療の力となりたい


廣田敦也
坂井橋クリニック 副院長廣田敦也(ひろた あつや)
1986年、三重県出身、川崎医科大学卒。四日市羽津医療センター、市立四日市病院、紀南病院、三重県立総合医療センター、名張市立病院と三重県内の基幹病院で循環器内科医師として勤務。2022年4月より坂井橋クリニック勤務。日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医。
坂井橋クリニック
〒511-0912
三重県桑名市星川1011-1
TEL:0594-31-4553
生まれ育った三重県で、幅広い医療を担う

私は三重県・桑名市の坂井橋クリニックで、副院長を務めています。開院は1909年と明治時代の後期で、私の曾祖父が開業しました。それから長く地元の方々に支えられ、現在は院長である父とともに、診療にあたっています。
私自身は循環器内科を専門としていますが、当院では一般内科のほか、小児科、一般外科にも対応します。点鼻薬や目薬の処方もしますし、ケガの縫合なども行います。やはり地域のクリニックというのはお子さんからお年寄り、さらにさまざまな症状の方が来院されますから、何でも対応できなくては話になりません。もちろん患者さんの状態によっては専門の病院におつなぎし、そこでより高度な治療を受けられるようサポートしています。
こうしたやり方は当院の伝統的なスタイルなのですが、私が学んだ三重大学医学部の教育方針によるところも大きいですね。医療の現場では人材不足が深刻で、特に三重県は全国的にも医師不足にあえいでいます。そのため三重大学医学部では、医師1人で多くの患者さんに対応できるような教育方針がとられているのです。
責任は重いがやりがいのある、循環器内科医

私が医師を志したのは、なんといっても父の影響です。子どもの頃は教師になりたいと考えていたこともありましたが、その頃から患者さんと身近に接し、手を尽くして治療にあたり、患者さんから感謝される父を見てきました。その姿は私の目に、とても誇らしく映ったものです。明治時代から続く医師の家系ということもあって、自分自身が医師になることに迷いはありませんでした。
その中でも循環器内科を選んだのは、「人の命に直結する診療科だから」というのが理由です。循環器科には内科と外科がありますが、どちらも人の命に直結しますし、迅速な判断と処置が求められます。医師の責任は重大だけれども、それだけやりがいも大きいはずだ…そう考えて、この科を選びました。
その後、三重県内のいくつかの基幹病院に勤務し、10年ほど経験を重ねたところで、選択を迫られることになります。専門である循環器内科をさらに深く追究するか、あるいは地域医療の道を選ぶかのいずれかです。少々迷いはしたものの、いろいろな病気を診られる医者は地域に必要だと考え、この道を選んだ、というわけです。
修業時代には、先ほどお話しした三重大学の教育方針もあって、自分の専門以外の科にも対応できるよう、幅広い知識と技術を身につけてきました。この経験が、今の診療に大いに役立っていると思います
「患者さんを診る」ことは、初代からの伝統

院長である父は糖尿病専門医であり、ベテラン内科医でありつつも、それこそ領域外の疾患でさえも診てきました。また私は循環器専門医としての知識と技術を持っています。糖尿病はさまざまな合併症が起こりやすく、心筋梗塞など循環器疾患との関連も深いものですから、2つの分野の専門家が揃っていることは当院の強みであり、地域の皆さんから信頼をいただいている理由のひとつだと思います。
また「病気だけでなく患者さんを診る」というポリシーも、初代から伝えられてきた伝統的な特徴といえるでしょう。
病院にやってくる患者さんは、皆さん不安を抱えています。どうも体の調子がスッキリしない、良からぬ病気だったりしないか。元通りの元気な自分に戻れるのか。そうした不安は必ずありますし、それ以前に「どの科を受診すれば良いのか分からない」という方も数多くおられます。ですから患者さんの体の状態や生活状況などを踏まえて診療にあたるようにしています。時には他の診療科…たとえば婦人科や整形外科を受診したほうが良い、ということもありますから、そうした場合には理由をしっかり説明して、他の病院を紹介しています。
当院は地域のかかりつけ医院ですから、まず患者さんがどういう状態なのかを見きわめること、その上で治療の道筋をつけていくことが大切だと思っています。また相談ごとに対しては、「大丈夫」「心配いりません」といったふわっとした言葉でなく、できるだけ具体的に説明して、安心していただくよう、心がけています。
敷居の低いクリニックであるため

どんな病気でも、早期発見・早期治療が重要です。ですから少しでも体の異変を感じたら、すぐに医師の診察を受けてほしい…というのが、私たち医師の本音です。ですが多くの方々にとって、病院というのは行きにくい場所でしょう。さほど大きな自覚症状がなければ、なおさらです。そこで当院では、少しでも患者さんに身近に感じていただけるよう、ホームページやSNSで情報発信をしています。
日本でSNSが普及し始めてからそろそろ20年ほどになるでしょうか。今では40代、50代の方々もSNSを使いこなしていますから、糖尿病や循環器疾患の注意喚起をするには、SNSは適したツールでしょう。とはいえ、あまり硬い話ばかりでは逆効果ですから、おもに休日の写真や遊びに行った話など、軽い話題を中心にし、気楽に見ていただける記事をアップしています。まださほどの反響があるわけではありませんが、今後もこの方針で長く続けて、患者さんにとって敷居の低いクリニックになれればと思っています
時代の進化に歩調を合わせることも重要
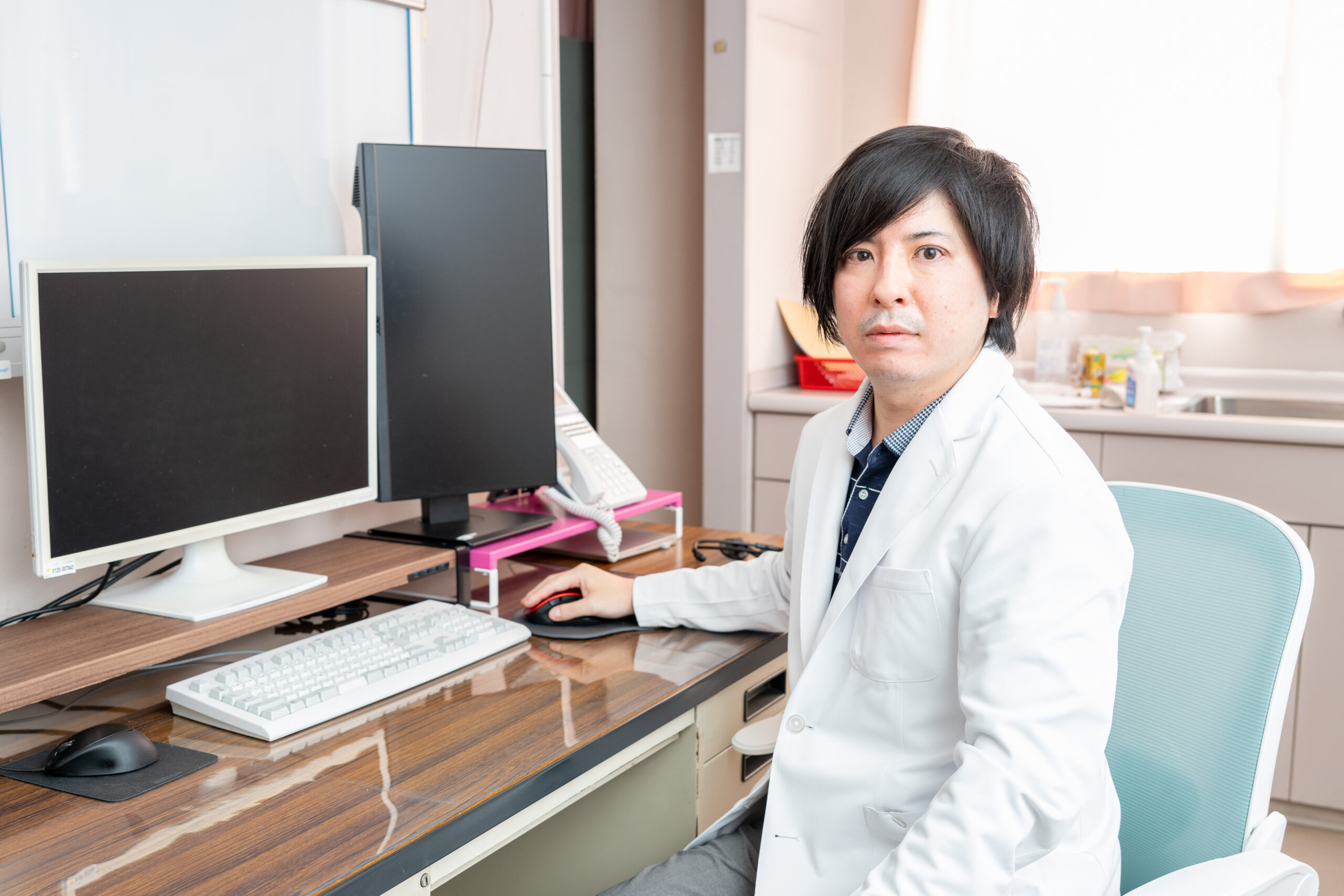
医療を取りまく環境は、時代に合わせて変化しています。たとえば話題になっている医療DXは、どんどん進めていかなくてはならないでしょう。ただでさえ人手不足なのですから、それを補うためにはDXによる業務効率化は不可欠です。これは医療の質の向上とスタッフの負担軽減になり、最終的に患者さんの利益になることですから、積極的に推進していくつもりです。
またデジタルツールでいえば、基幹病院の先生方や他の診療科の先生方とオンラインで相談したり、医師同士のネットワークで情報収集したりといったことは日常的に行っています。これは昔と比べて大きく変わったところですね。患者さんの中にはさまざまな理由で来院しにくい方もおられますから、ご希望があればオンライン相談にも対応しています。
このように、守るべきものはしっかりと守りつつ、時代に合わせて進化するツールや新たな仕組みはどんどん取り入れて、患者さんの利益につなげていけるよう、努めています。
三重の良さを知り、活力を高めていきたい

先ほども触れましたが、三重県の医療人口は少なく、全国規模で見ると下から何番目というレベルです。これは医療に限った話ではなく、他の業界でも同様かもしれません。三重には四日市や津といった大きな都市がありますが、一方で人口の少ない地域もあります。そのため高校や大学を卒業して、近隣の大阪や名古屋、さらには東京に出て行く若者たちは多いと思います。私自身は地元愛が強かった事もあり、ずっと三重で働き、暮らしてきました。ただ、これから社会に出て行く若者たちには、ぜひ三重の良さを知ってほしいと思います。
ただ、これから社会に出て行く若者たちには、ぜひ三重の良さを知ってほしいと思います。おそらく一度県外に出てみると、それが実感できるかもしれません。素晴らしい自然環境や穏やかな人情、山海の幸など、三重ならではの美点はいくつもあります。そうした美点に気づき、それを周囲にアピールしていただきたい。そしてできることなら再び三重に戻って、生まれ故郷で活躍してほしい。それが、三重の活力をさらに高めることにつなげていけるのではないか。私はそう思っています。
坂井橋クリニック
https://sakaibashi-clinic.jp/