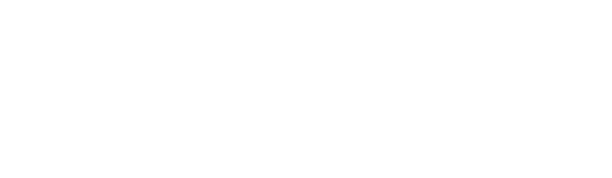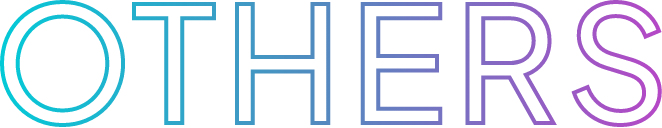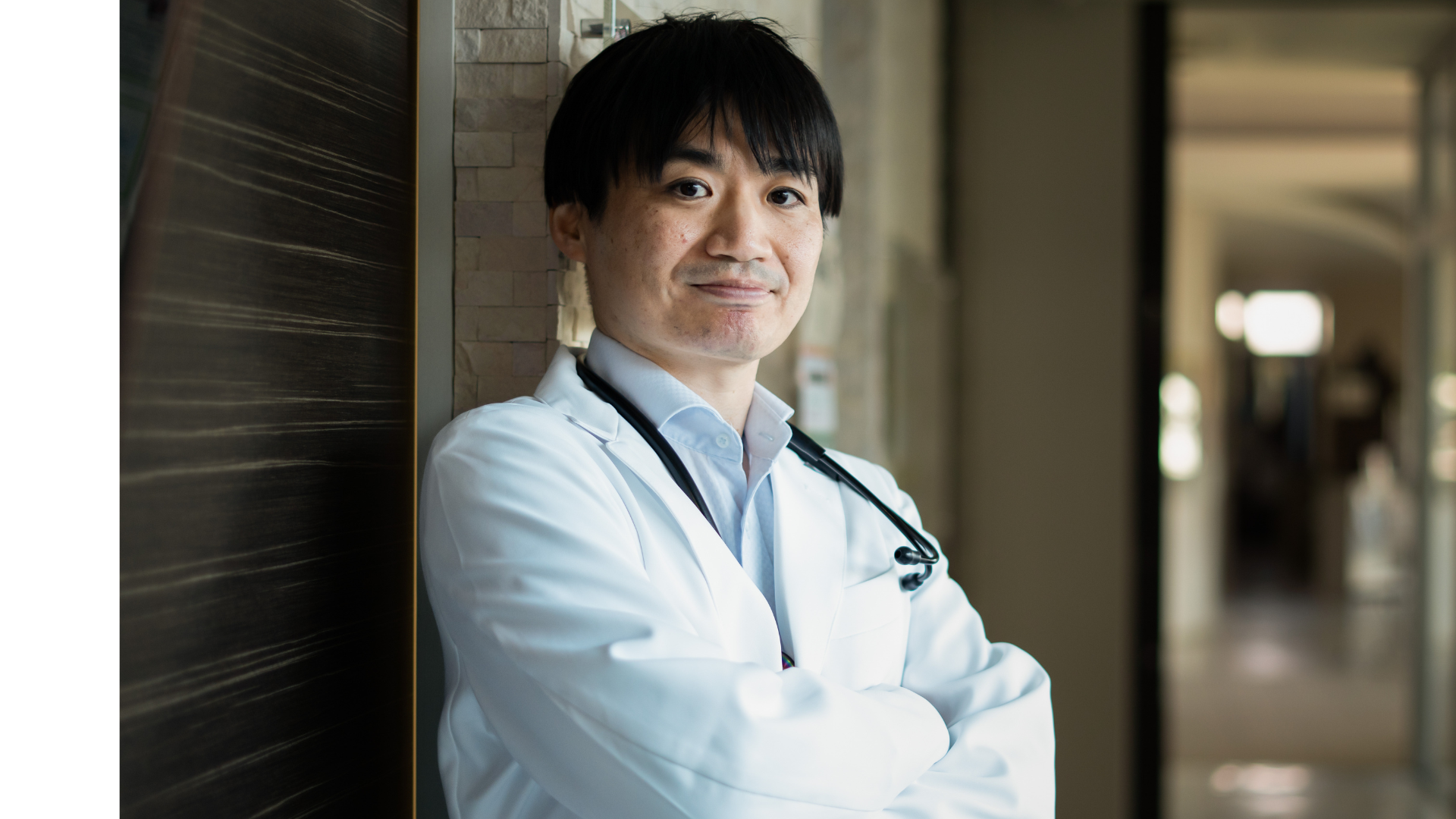三重県の医療の「最後の砦」はわれわれが守る


佐久間肇
三重大学医学部附属病院 病院長佐久間肇(さくま はじめ)
1960年三重県出身、1985年三重大学医学部卒。三重大学病院、福井医科大学病院で放射線科のトレーニングを受け、1991-1996年カルフォルニア大学サンフランシスコ校で心臓MRIの研究開発と臨床応用に従事。1996年に三重大学に戻り、2012年に放射線科教授。2013年に三重大学医学部附属病院副病院長(研究担当)に就任。以降2024年まで、研究・経営・診療担当として継続して同職に就く。2024年、三重大学理事、副学長。2025年4月、同病院長に就任。1996年に三重大学病院に戻り、学理事、副学長。2025年4月、同病院長に就任。
これまでの知見と経験を活かし、組織の舵取りを担う

2025年4月から、三重大学医学部附属病院の病院長に就任しました。2015年から長らく副病院長を務め、研究、経営、診療と異なるポジションから病院運営に参加させていただきましたが、今後は病院長という重責を担うことになり、身の引き締まる思いです。これまでの副病院長としての知見と経験を活かし、組織の舵取りにあたる所存です。
病院長として為すべきこと、為したいことは多々あるのですが、大きな視点から申し上げれば、三重県における先進的な医療の提供とその安全を守っていくことが重要です。これは三重大学が策定した中期計画「アクションプラン2030」に沿って、推進されています。
他の多くの業界と同じく、地方の医療は人材不足に悩まされています。さらに、医師等の地域偏在に加えて、診療科間での人材の偏在もあります。大学病院では地域に貢献するために、関連施設に医師を派遣し、地域の医療サービス網が維持できるように対処しています。当院に関していえば県内のほとんどの病院に医師を派遣していますから、大学病院と一般医療機関とのつながりが他の県よりも強い、といえると思います。
これは当院の強みでもありますから、このつながりをさらに強固にし、三重県全体の医療を支えていくことが、附属病院の病院長としての重要な責務と考えています。
高度な先端医療の提供と、次世代を担う人材育成がカギ

当院は大学医学部の附属病院であり、大学病院は診療・医学教育に加えて研究機関としての役割を持ちます。私どもは海外を含めて常に最新の技術や情報を取り入れ、最先端の医学研究を行ってきました。そうした研究成果や新しい技術は直ちに現場に導入できるものばかりではありませんが、時間をかけて磨き上げられて、安全性が確立されたうえで、臨床で活用されます。当院では多くの高度医療、先端医療が実施されており、県内あるいは周辺地域の方々が、わざわざ大阪や東京まで出向かずとも、当院で国内最先端の医療を受けられるように、体制を整えております。当院は三重県内のがん診療や救急を含む医療の最後の砦の役割を果たしており、県民の皆さんの期待にしっかり応えなくてはと思っています。
もうひとつ注力すべきは、人材の育成です。先ほども少し触れましたが、医療人材の不足は医師のみならず、看護師をはじめとする各職にも及んでおり、特に地方ではますます深刻な問題となっています。少子化と人口減少は今後さらに進行していきますので、こうした問題を解決するためには、医療DXによる医療の効率化と質の向上が不可欠です。三重大学では医療DXの推進に力を入れており、PHRの導入や遠隔医療の推進、三重県内の医療機関を結ぶクラウド型の紹介・逆紹介システムの開発などを推進し、デジタル技術を活用した業務プロセスの簡素化やヒューマンエラーの排除、病院での待ち時間の解消など患者さんへの医療サービスの向上などに取り組んでおります。さらにはそうした変革を推進できるDX医療人材の育成も重要な課題と考えており、地域医療のスマート化を進めているところです。
当院が持つアドバンテージをさらに高める努力を

私は放射線科医なのですが、一般の方からすると、放射線科というのはX線やCT、MRIなどを使って画像診断をするところ、という認識をお持ちだと思います。確かにその通りなのですが、ひと言で画像診断といっても、撮影した画像から、それぞれの患者さんにとって最適の治療に結び付く情報を引き出して、どこまで正確な診断ができるかは、最新の装置を使いこなして診断する医師の力量に左右されるところが大きいのです。当院の画像診断、特に循環器系については日本国内でもトップレベルで、国内だけでなく海外からも多くの放射線科医や循環器内科医の方々が、長い方では数年間勉強にいらっしゃいます。
このように、大学病院は全領域で高いレベルを維持することはもちろんですが、国内トップの抜きんでた領域をできるだけ多く持つことも、優れた医師を輩出する医療教育機関として大変重要ではないかと私は思っています。若い医師たちは、三重県から出て行った方が高いレベルの医療を習得できると考えがちなのですが、国内トップレベルの分野を増やしていけば、三重県の病院で働きたい、当院で勉強したいというモチベーションにつなげることができ、医療人材の県外流出を抑え、流入を高める効果も期待できるからです。
先ほどのDXと関連して、県内の医師不足地域における内視鏡検査や手術を医療DXを使った遠隔指導や、当院に三台ある手術支援ロボット「ダヴィンチ」のクラウドによるオンライン教育システムを構築するなど、若手から中堅の医師の支援にも力を入れています。後者については日本初の試みですが、新時代を担う医療人の効率的な教育という点で、きわめて有効だと考えています。
経営上の問題を多角的な施策で乗り越えていく

現在、日本の医療機関の経営は大病院から診療所まで規模を問わず、厳しさを増しており、国立大学病院も8割以上が赤字です。国立大学病院の収入は民間病院と同様に保険診療が大部分を占めており、光熱費を含めた物価や教職員人件費の上昇は、診療報酬の増加をはるかに上回っています。都市部の病院は物価や人件費がもともと高いため、インフレの影響を受けやすく、人口減少が進んでいる地方の病院では患者減少により稼働率が維持できない等、地域を問わず病院経営はかなり厳しい状況が続いています。当院は人事院勧告に準拠して教職員の給与を昨年4月にさかのぼって引き上げており、令和6年度の収支はわずかに赤字となっていますが、がん診療を中心に当院の高度医療に対するニーズは高く、また「津市の市民病院」としての役割も果たしているため、新入院患者数は引き続き増加するなど、医療需要の観点では比較的恵まれております。
私も副病院長や経営担当理事として経営に参画しており、経営状況の厳しさは痛いほど理解しています。しかし、三重県の患者さんの高度で質の高い医療に対するニーズに応えていくためには、当院の収支を黒字化し、インフレに応じて教職員の皆さんの給与を上げていく必要があります。私は病院全体で頑張ればそれは可能と考えています。業務の効率化やDXの推進は対策の一例ですが、現在の国立大学病院経営の状況は、院長の打ち出すトップダウンの施策だけで大きな改善が得られるものではありません。まず、事務部門のIR機能や経営力を高め、詳細なコストを含めた経営データを事務部門が提示し、それを基盤に各診療科が稼働額だけでなく収益状況を把握して、打てる手を自主的に打っていく環境を作ることが重要です。さらに、自院のブランド力を増強し、それを県民の皆さんにうまくアピールしていくことも大事だと思います。
環境をさらに洗練させ、次世代の方々と医療を支えたい

日本は世界的にみても貴重な皆保険制度があり、高度な医療を誰でも比較的安価に受けられる体制ができています。ただし、最近3年間において医療DXを推進してみると、日本の医療分野のデジタル化が非常に遅れていことを痛感します。15年~20年前に共同研究で何度も訪れたフィンランドでは当時から国全体で医療のデジタル化が進んでいましたし、また国を挙げてのデジタル化を実現しているエストニアなどは、日本とは比較にならないレベルに達しているようです。自治体や関連病院と連携しながらDXを推進し、より洗練された医療DX環境を構築するのは、地域医療に対する我々の責務だと思っています。
また医療人を目指す若い方々には、東京や大阪に出ていかなくても三重大学で最先端・最高水準の医療技術に触れ、それを身につけることができるということを知っていただきたいですね。そのための環境整備にも、われわれは大いに力を入れています。三重県の医療を支えるためにも、これから社会で活躍する若い皆さんと、ともに力を尽くしたいと思っています。
三重大学医学部附属病院
https://www.hosp.mie-u.ac.jp/