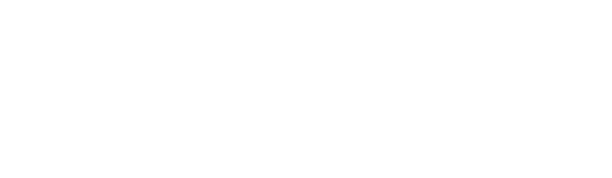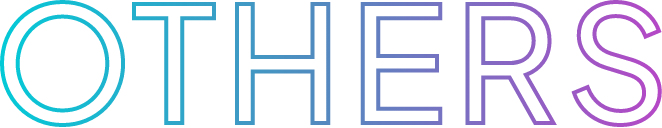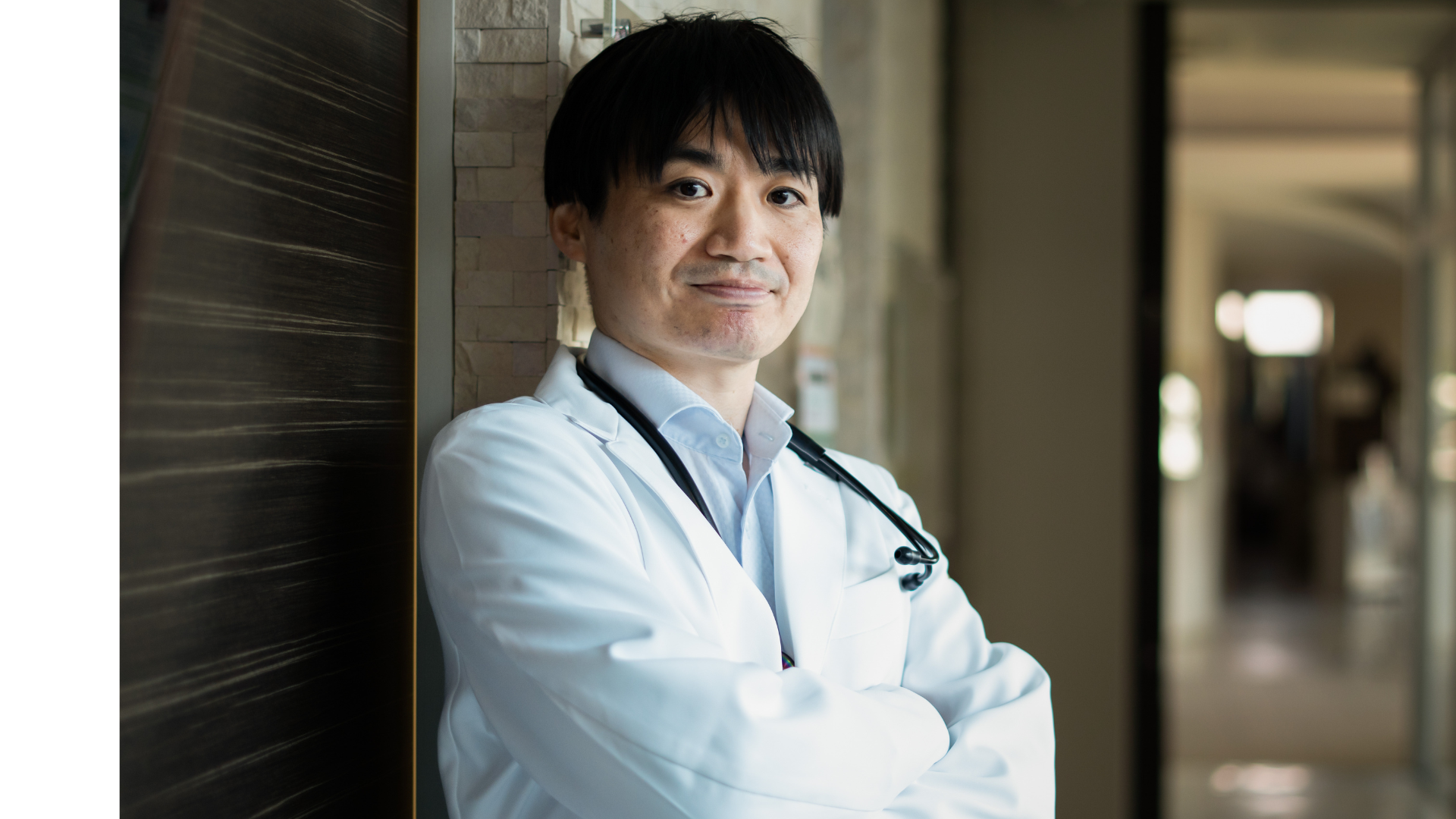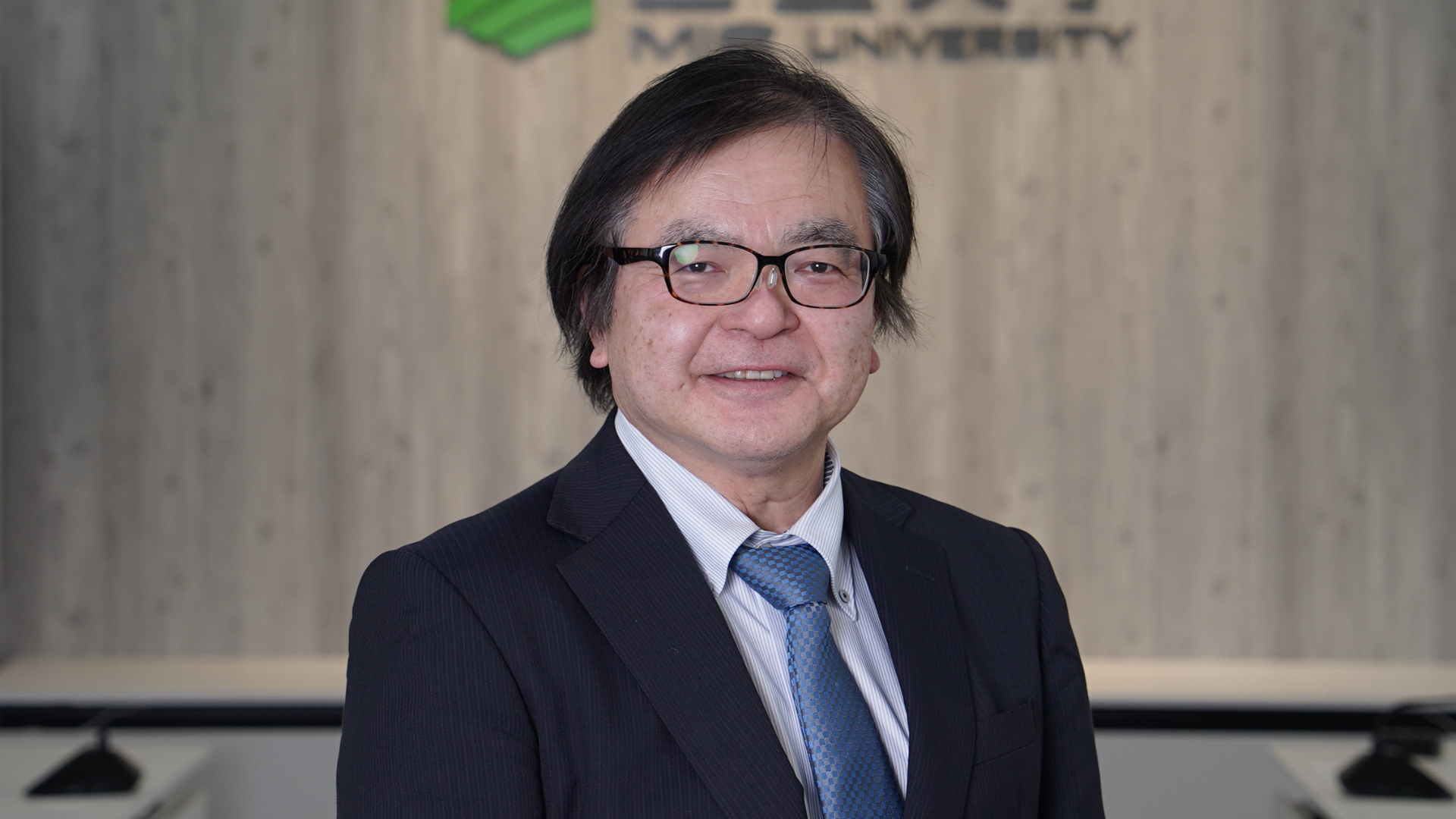建設業界のイメージを大きく変える、そのきっかけとなりたい


川又勝太
株式会社川又興業 代表取締役川又勝太(かわまた しょうた)
1994年、三重県出身。中学校卒業後、建設業に飛び込み、足場工事に従事する。2015年、プラント鳶に転職、コ ンビナートでの高所作業や重量物の据付・撤去を手がける。2020年に独立、川又組として個人事業を開始。2023 年、川又興業として法人成りし、同社代表取締役に就任。
株式会社川又興業
〒 512-0906
三重県四日市市山之一色町2080-2
TEL:0059-340-4017
早く社会に出たい一心で、建設業界に飛び込む

父親が大工だったこともあって、私には子どもの頃から職人に対する憧れがありました。ことに十代の頃はいわゆるヤンキーでしたから、建設業の作業服姿がかっこよく見え、「中学を出たら建設業界で働こう」と思っていたのです。もともと学校の勉強は苦手でしたし、高校に行って時間とお金を無駄に使うくらいなら、早く社会に出て仕事を覚え、独立を目指したほうがいい…という思いもありました。そのため中学卒業と同時に友人を頼り、足場工事の会社に就職することができました。
足場工事というのは、ビル建築や外装補修工事の際に足場を組む仕事です。もともとは鳶(とび)職の仕事の一部だったそうですが、私が業界に入った頃には、足場の組み立てとその解体を請け負う「足場屋」として専門化されていました。
この会社には5年ほど勤めて、鳶職の基本的な仕事を身につけたのですが、何しろ足場屋は足場の組み立てと解体を繰り返すばかりで、他の仕事を覚えることができません。そこで仕事の幅を広げるために、私の兄が立ち上げた「プラント鳶」の会社に転職しました。
「プラント鳶」の仕事を覚え、ひょんなことから独立

私が生まれ育った三重県・四日市市は、日本有数の工業地帯として知られています。そこでは数多くのプラントが パイプラインでつながり合って、コンビナートを形づくっています。当然、さまざまな機械類が稼働しており、それらのメンテナンスや更新、新規機器の据え付けなどの作業が発生します。そこで活躍するのが、プラント鳶です。プラント鳶はその名の通り、工業プラントの機械類の据え付け・撤去や、メンテナンスのための足場組みなどを専 門的に行う職種です。プラント内が仕事場ですから地上高10メートル以上といった高所作業が多く、重量物も扱うために危険度の高い仕事でもあります。反面、コンビナートのプラントは重要な社会インフラですから、自分たちの仕事が人々の生活を支えているというやりがいは大きいですね。
この会社には5年ほどお世話になりましたが、私のちょっとした至らなさから社長である兄と衝突してしまい、退職せざるを得なくなってしまいました。そのためまず個人事業として2020年に「川又組」を立ち上げ、2023年に川又興業として法人成りし、現在に至っています。
自分を支えてくれる周囲への感謝を忘れずに

独立した頃は本当に無我夢中の毎日でした。手持ち資金は乏しく、それこそ10円でも支出を抑えなくてはなりませんし、呑気に遊んでいるヒマなどありません。とにかくあちこちに顔を出し、ひとつでも多くの仕事をいただいてこなくてはならない。もちろん従業員は私一人しかいませんから、請け負える仕事は限られています。それでも私を見込んで仕事を振ってくださるお客様はありましたし、そうした期待には何が何でも応えなくてはいけない。周りの業者さんや職人さんに声がけをしたり手を貸していただいたりと、当時は本当に周囲の方々にお世話になりました。どんな仕事でもそうだと思いますが、一人の人間にできることなど、本当にたかが知れています。弊社の仕事も、手を貸してくれる専属の協力会社さんや下請けさん、何より社員の面々の力があるからこそ、できるのです。それを思えば、現在の自分は本当に恵まれていると思いますし、感謝しかありません。
もともと私は若い頃からやんちゃ坊主で、周りに迷惑をかけてばかりでした。ならこれからは、仕事を通じて人々の お役に立たなくては。そうした思いは今も強く感じています。
業界では異例の、社員への手厚いサポートを実現

ひと昔前の建設業は「6K」などといわれ、仕事はきつくて危険、休みが少なく給料が安い、見た目も汚くカッコ悪い…というイメージが定着していました。ですが私は、そうしたステレオタイプを破壊したいと思っています。そのためにできることを、すでに弊社では実践しています。
まず就労環境は政府が進める「働き方改革」の指針に沿って、ルールを設定しています。また社員一人ひとりに社用車を貸与して、自宅から現場に直行・直帰できるようにしています。これなら、社員の拘束時間をより短くすることができます。
建設業界は一般的なオフィスワークと違って事故やケガのリスクが高いこともあって、有資格者でないとできない仕事が数多くあるのですが、その資格を取得するためのサポートも行っています。未経験・無資格で入社した若い社員には、すぐに活用できる資格を7種類ほど、取得できる体制を整備しています。他にも仕事で使う道具や工具はすべて会社側で用意したり、ボーナス支給を年3回にしたり。頑張れば頑張っただけ収入に反映される仕組みを設けています。
これらのことは建設業界では異例ですし、はた目には大盤振舞にも見えるでしょう。ですが社員にはそれぞれの生活がありますし、家族を抱えている者もいます。それを思えば、時間的・経済的余裕をいかに社員に提供していくかは、会社が果たすべき重要な役割です。私としては決して特別なことではなく、当たり前のことだと考えています。
業界に根強く残る固定観念を払拭したい

私が大きな目標として掲げているのは、建設業界のイメージを変えることです。先ほどの6Kもそうですが、「建設業界ってこういうもの」という固定観念は、今も世間に根強く残っています。ですが私は会社を通じて「それは違うんだ」と発信していきたいのです。特に若い世代に対しては、さまざまな形で情報を届けていきたいですし、彼らに魅力を感じてもらえる会社にしていきたい。就業ルールの整備や福利厚生の充実は、その一環です。また「川又興業」という社名も、あえてその名を選びました。同業の方からも「何やら、いかがわしい会社に見られないか?」と心配されますが、それで良いのです。ゴツゴツしたいかつい社名とは裏腹に、社内環境がクリーンに整っている。そうしたギャップを狙ってのことです。
どこまでやれるか分かりませんが、建設業界は面白い、職場環境も整っている…そうしたイメージが一般化するようになれば良いなと思っています。私自身が、そのきっかけを作った人間になれるよう、まだまだ頑張らなくてはなりません。
社員に近く、本音を話せる存在でありたい

私は今でも積極的に現場に出るようにしています。これは現場が好きだから…ということもありますが、社員に近い存在でありたい、というのが大きな理由です。
社員間のコミュニケーションがうまくいかず、ギクシャクしていたり、ふさぎ込んで元気のない社員がいたりというのは、どんな会社でもあることです。そんな時、本人たちに尋ねてみても、決して本当の答えが返ってくるとは限りません。「最近様子がおかしいけれど、何かあったのか?」と聞いてみたところで「いや、別に何もありませんよ」で終わってしまうでしょう。
でも普段から現場に出て、社員と一緒に仕事をしていれば、気安く言葉を交わすことができますし、お互いの距離を縮めることもできます。そうすれば、彼らの本音に触れ、悩みや問題を解決する手助けがしやすくなると思うのです。
程度の差はあっても、人には悩みごとや困りごとはつきものです。そして社員を守り、彼らの悩みや問題を解決するのは、社長である私の役割です。この姿勢は、今後も維持していきたいと思っています。
充実した生活と安心して働ける環境がある

三重県というのは地理的に、大阪と名古屋といった大商圏が近いため、若い方々はこれらふたつの都市へと出ていくことが多いようです。これは人それぞれの判断ですから、良い悪いというものではありません。ですが私自身は、この三重県・四日市市で踏ん張りたいと考えています。未熟だった私を受け入れてくれたのも、苦しい時に助けてくれたのも、この街であり、この街に住む方々でした。その恩に報いるためには、仕事を通じて感謝を伝え続けていくことだと思うからです。
ただ、若者の県外流出という課題については「魅力的な企業が県内に少ない」ということも要因に挙げられるかもしれません。ですから弊社が若者にとって魅力的な会社になれば、「ここで働きたい」という声も増えていくでしょうし、業界のイメージを変えていくこともできるはずです。
もしもあなたが進路に迷い、「建設業って、どうなんだろう?」と考えているなら、ぜひ弊社のドアを叩いてください。 充実した生活と安心して働ける環境を用意して、お待ちしています。
株式会社川又興業
https://www.kawamatakogyou.com/